第1回
保険薬局におけるがん薬物療法の服薬指導のポイント
PDF
がん治療を受ける患者さんの服薬指導は、治療やそれに伴う副作用に対するケアの理解度、心理状態などに配慮しながら行うことが重要です。がん薬物療法の服薬指導で大切なのは患者さん一人ひとりの状況に合わせた個別指導であり、薬剤師にはがん薬物療法以外のことでも気軽に相談できる窓口としての役割が求められます。
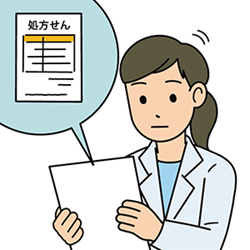
がん患者さんの思いを傾聴しましょう
患者さんにがん薬物療法を安全に、安心して継続してもらうためには、服薬指導で説明しなければならないことが多くあります。しかし、薬剤師が初回の服薬指導でその内容を一度に伝えてしまうと患者さんはついてこられず、置き去りになってしまうことがあります。服薬指導におけるコミュニケーションは、患者さんの理解度や反応を見て、一方的にならないようにすることが大切です。患者さんに寄り添いながら、ともに一歩一歩階段をのぼるように薬や副作用のケアについて患者さんの理解が深まるように進めましょう。
●服薬指導は患者さんの心の準備と足並みを揃えて
がん患者さんは、がんになったことへのショックやこれからはじまる治療の内容、将来への不安を抱えたまま治療に臨まざるを得ない状況にあることが少なくありません。初回の服薬指導時に抗がん剤や副作用、ケアについて説明をしても、患者さんがそれを受け止め、理解する心の準備ができていないこともあります。
患者さんが強いショックや心配を抱えているなかで副作用の説明などをすると、患者さんの不安がかえって増してしまい、治療拒否などにつながってしまうこともあります。
薬剤師が患者さんに抗がん剤の情報を伝える前に、まずは薬剤師が患者さんのことを理解するように心がけましょう。患者さんががんと診断されたことをどのようにとらえているのか、いまの悩みや不安なことは何かを聞き取り、不安を軽減するかかわりが大切です。がん患者さんの思いを傾聴し、共感する姿勢で向き合うことが患者さんのがん治療をサポートする最初のステップであることを忘れないようにしましょう。このプロセスを飛ばしてしまうと、薬剤師と患者さんのコミュニケーションがすれ違ったままがん治療が進んでしまいます。
●患者さんの表情から得られる情報も大切に
患者さんの話し方や表情を観察して患者さんの思いを汲むことも服薬指導を行う薬剤師に求められる重要なスキルです。がんと診断された直後には頭が真っ白になってしまい、薬剤師の話を聞いているように見えても実際には何も理解できていないことがあります。声が弱々しい、不安そうな目をしているなど、声や表情から察知できる言葉以外の情報も見逃さないようにしましょう。
●患者さんからの情報収集の流れ
患者さんの情報は、処方箋や検査値から収集をはじめます。そこからさらに必要な情報を絞り込み、患者さんとの会話を通じて引き出していきます(表1)。
表1 情報収集のポイント
| 処方箋 | 患者さんから受け取った処方箋に抗がん剤が記載されていた場合、そのほかにどのような併用薬が処方されているか、用法・用量や処方日数、年齢・性別、処方箋を発行した医療機関などを確認する。得られた情報からがん種やレジメンを絞り込むことで、経口の抗がん剤だけでなく点滴による外来化学療法を受けているかどうかも推測できる |
| 検査値 | 抗がん剤は、患者さんの年齢や体重、肝障害、腎障害の有無による用量変更があるため、検査値を確認したうえで処方監査を行う。がん患者さんは治療に入ると体重が減少して初回に設定された用量では過量投与となる可能性がある。薬剤師はがん治療中の検査値をチェックし、適正量となっているかどうかを確認する |
| 患者さんへの聴取 | 患者さんがどの程度がんやその治療について理解しているのかは、その後の服薬指導に影響する重要な情報である。しかし、がんと診断された直後はがんであることを認めたくなかったり、強い不安や落ち込みを感じたりして医師から病状や治療の説明があっても正確に理解できていない患者さんは少なくない。医師が同じ説明をした場合でも患者さんによって理解度が異なることを踏まえて聴取する必要がある |
●服薬指導で起こりやすいコミュニケーションのエラー
患者さんへの質問は、目的に応じてコミュニケーションスキルを使い分けることが大切です。患者さんの理解度を確認する際のコミュニケーションを「はい/いいえ」で回答ができる、「閉じた質問」、「はい/いいえ」では答えられず患者さんに自由に表現してもらう「開いた質問」のパターンでみていきましょう。
【コミュニケーション例:閉じた質問】

「医師からがんやこれから受ける治療について説明を受けていますか?」

「はい…。先生に聞きましたので大丈夫です」
【コミュニケーション例:開いた質問】

「医師や看護師からはどのように説明をされましたか?」

「乳がんのステージIIIと診断され、手術を受けました。ただ、手術で取り切れなかったがんがあるので、抗がん剤の治療が必要だと言われました」
患者さんが、がんやその治療をどの程度理解しているかを確認するコミュニケーションに適しているのは、患者さんが自由に表現できる「開いた質問」です。患者さん自身に説明してもらうことで、理解できていることと理解できていないことが明確になり、薬剤師が再度説明する必要のある項目を絞り込むことができます。
一方、閉じた質問で得られる情報は「医師からがんや治療の説明を受けた」ことのみで、患者さんが理解できているかどうかまではわかりません。そのまま薬剤師が服薬指導に入ってしまうと、薬剤師が考える患者さんの治療への理解度と、実際の理解度に差が出てしまうことがあります。副作用ケアがうまくできなかったとき、薬剤師は「きちんと説明したはずなのになぜ…?」と、指導に不安を感じるかもしれませんが、患者さんは「説明を聞いていない」「何を言っているのかわからなかった」と考えているかもしれません。目的に応じて質問の仕方を変えてコミュニケーションのエラーを防ぐことが大切です。
●「閉じた質問」「開いた質問」の詳しい解説はこちら
スムーズな服薬指導につながるコミュニケーションスキル
患者さんとの会話の糸口をみつけるヒント
保険薬局に来局するすべてのがん患者さんががんであることを受け入れ、積極的に治療を受けたいと思っているとは限りません。なかには自分のがんのことを話したがらない患者さんもいます。
会話をしたがらない患者さんへの対応では、話を聞き入れてもらえる環境をつくるために天気や季節の話題など、がん治療とは関係のない話から会話の糸口を見つけていきましょう。がんであることを受け入れられない、治療を受けたくないと思っている患者さんでも関心のある話題からはじめることで会話の流れがつくりやすくなります。
【コミュニケーション例:天気の話題から】

「今週はずっと暑い日が続いていますね」

「そうだね。毎日大変だよ」

「本当に大変ですね。今週はどのように過ごされていたのですか?」

「今日の通院以外は自宅でのんびりしていたよ。エアコンは使いたくないけれど、ここまで暑いと使わざるを得ないよね」

「ご自宅で過ごされていることが多いのですね。ご自宅ではどんなことをされているのですか?」

「とくに何もしていないよ。がんと言われてから外に出る気力がなくなってしまって趣味の絵画もやめてしまったし…」

「そうですか。それはおつらいですね。がんと診断されたときはどのようなお気持ちでしたか?」

「元気が取り柄だと思っていたからがっかりしてしまったよ。しかも手術だけで終わりだと思っていたのに、抗がん剤治療もやらなくちゃいけないなんて…。副作用のことも心配だし、家を出る気力もないよ」
この例では、天気からがんと診断されたことに対する思いまで、患者さんの受け答えから得た情報を次の話題の糸口にして会話を続けています。天気の話題から日中はエアコンの効いた室内でのんびり過ごしていたという情報を得ることができ、その情報から自宅でどのように過ごしているのかを聞き、がんと診断されたことによる不安な気持ちやいまの思いを引き出しています。
天気や季節の話以外では、仕事も会話のきっかけにしやすい話題です。たとえば患者さんが漁業関係者であれば、「この時期に近海でよくとれるのはどんな魚ですか?」といった簡単な質問から会話をはじめるとよいでしょう。患者さんの関心事を話題にすることで、患者さんも気負うことなく話すことができます。
●聞きにくい話は周辺情報からアプローチしましょう
がん薬物療法の説明では、患者さんの個人的な話題に触れなくてはならない場面もあります。たとえば、妊孕性が障害される抗がん剤を使う場合、その後のライフプランにも影響が出ます。がんと診断されてショックを受けている患者さんから妊娠や出産についての考えを聞き出すのは難しいことですが、薬の専門家である薬剤師が丁寧に説明をするためにも確認しなければならない項目です。
聞きにくい話をするときには、周辺情報をきっかけにしてコミュニケーションを取り、会話の流れをつくってから本題に入るなどの工夫が必要です。
患者さんは一人ひとり置かれている環境やライフプランが異なります。がんの薬物療法を受ける患者さんは、「将来子どもが欲しいけれど、自分の生命を守るためにはあきらめるしかない」など、医療従事者に本音を打ち明けることをためらうことがあります。また、すでに子どもがいても妊孕性の温存を希望していたり、生殖適齢期でも妊娠や出産は考えていなかったりと、患者さんの思いは千差万別です。
がん薬物療法に伴う妊孕性への影響は、主治医からの説明が十分でないケースもあります。薬剤師ががん薬物療法による影響を伝えたうえで患者さんの意思を確認し、将来子どもを望む患者さんには医師への相談を勧めましょう。
患者さんに応じたアプローチの方法を探しましょう
最初はがん薬物療法や副作用ケアの理解度が低かった患者さんでも、繰り返し指導を行うことで理解が深まっていきます。その変化はコミュニケーション時のリアクションや表情、声の張りなどで感じ取ることができるでしょう。しかし患者さんからの返答に「うーん…」「あぁ…」などのつなぎの表現(間投詞)が多い、表情が曇っている、声が小さいという場合には、わかっているつもりでも実際には理解不足の可能性があります。
●電話によるフォローアップの活用
薬剤師が「まだきちんと理解ができていないのではないか」と感じた場合は、電話でのフォローアップが有効です。場を切り替えて、落ち着いて過ごすことができる自宅で話をすることで、患者さんの理解が深まることもあります。電話でのフォローアップでも理解度が低いと感じた場合は、次回来局時の指導で再確認をします。理解度を確認しながら次のステップに進み、治療を完遂できるように支援しましょう。

●患者さんが受け入れやすい言葉遣いや話し方
情報は伝える人の言葉遣いや声の高さ、大きさなどによって患者さんの受け止め方が変わります。これは指導を受ける患者さんの性格も影響するでしょう。とくに抗がん剤の副作用に強い不安がある患者さんに対して一度の服薬指導ですべての副作用を説明したり、「この抗がん剤は必ず吐き気が出ます」といった強い言葉を使ったりすると混乱して不安が増してしまいます。服薬指導の際には患者さんの副作用に対する感じ方や治療を受けることをどのように感じているかを引き出し、個々の患者さんによってアプローチの方法を変えてみましょう。
薬剤師が一生懸命服薬指導を行っても、それが一方通行となってしまえば必要な情報が伝わりません。患者さんが正しく服薬できなかったり、副作用への対応が遅れたりすることは治療中断を招くリスクとなります。コミュニケーションを通じて患者さんに寄り添い、共感する姿勢で服薬指導にあたることががん薬物療法を担う薬剤師の役割です。
●薬剤師の服薬指導の不安は患者さんに伝わる
薬剤師が抗がん剤の服薬指導に不安を感じていると、その不安は患者さんにも伝わってしまいます。患者さんに「この薬剤師さんなら何でも相談できる」と感じてもらうためには、抗がん剤の知識を常にアップデートし、患者さんにわかりやすく説明できるスキルを身につけることが大切です。がん薬物療法の知識や経験を客観的に評価する材料となる認定資格には、がん専門薬剤師、がん薬物療法認定薬剤師、外来がん治療認定薬剤師があります。学会への参加や研修の受講などを通じて知識を身につけて患者さんから信頼される薬剤師を目指しましょう。

<文献>
| ・ | 宮田佳典・中信がん薬薬連携推進ワーキンググループ:保険薬局薬剤師のための もうビビらない!がん関連処方対応術.南山堂,2019. |

静岡県立静岡がんセンター 薬剤部 副薬剤長
石川 寛 先生
2001年東京薬科大学薬学部薬学科卒業後、メディオ薬局に勤務。2004年、静岡県立総合病院に入職し、2008年から静岡県立静岡がんセンターでがん薬物療法に携わる。日本医療薬学会がん専門薬剤師。静岡県病院薬剤師会学術部がん専門薬剤師部門委員長ほか。
この記事は2025年8月現在の情報となります。

