
患者さんと接する家族へのアドバイス
がん患者さんの家族は、患者さんに対してできるだけ食事をしっかりとることを勧めたり、バランスの良い食事にこだわったりすることがあります。しかし、味覚障害の症状がある患者さんで、分食でなければ食べられない、味のしない食事に食べる気がわかないという人は少なくありません。無理に食事をとらせようとするのは、さらに食事を苦痛にする原因ともなるため、家族には味覚障害の症状が改善するまでは可能な限り患者さんの要望に沿うように伝えましょう。
●調理の役割の見直し
家族のなかで患者さんが主に調理を担ってきた場合、それをすべてほかの家族が担ってしまうと患者さんの家庭での役割が失われたような気持ちになってしまうことがあります。患者さん自身が望む場合にはがん治療期間中は一緒に調理をする、あるいはこれまで通り患者さんが主に調理を担い、味つけのみ家族が行うなど、患者さんに合ったサポートの形を家族、患者さんとともに探していけるようにアドバイスすることが大切です。

食事をとる環境の調整
患者さんは、味覚障害があることで食欲が低下し、食べることに対する楽しみの減少や孤独感が強くなるなど、心理的な問題を伴っている可能性があります。食べることに意識を向けすぎることがより心理的な負担になることもあるため、普段通りを心がけるように伝えましょう。
また、食事をとる前に唾液分泌を促すことで味を感じやすくなることがあります。唾液腺マッサージを行うことも有効ですが、会話をすることでも唾液分泌を促すことができます。食卓を楽しめる環境づくりを大切にするようにアドバイスしましょう。
●献立を考えるときのヒント
味覚障害のある人向けのレシピなどを参考に、患者さんが食べやすいものを献立に加えるとよいでしょう。また、味つけを濃くすることで味を感じやすくなる場合には、同じ献立で家族のものを取り分けた後に塩味を加えるなどして味つけを変えることで、主に調理をする人の負担が軽減できます。
味つけが家族間で合わない場合には、鶏むね肉のハムのようにたんぱくな味のものを準備し、ソースの種類を増やして患者さんも家族も好みのものを選べるようにするなどの工夫も効果的です。同じ食事を家族で楽しむことができ、患者さんも食事を楽しむ気持ちになれることで、心の負担も軽くなり、がん治療を乗り切る力となります。
<文献>
| ・ | 石川寛著・野村久祥編:がん薬物療法の「スキマ」な副作用~困った症状と正しく向き合う!~ 第3回味覚障害(味覚異常).月刊薬事,じほう.60(4):107-113,2018. |
| ・ | 栗橋健夫:栄養を科学するイラスト解説 味覚障害のメカニズムを探る! 唾液と咀嚼のはたらき.Nutrition Care,メディカ出版,14(8):16-22,2021. |
| ・ | 任智美:栄養を科学するイラスト解説 味覚障害のメカニズムを探る! 全身性疾患と味覚障害.Nutrition Care, メディカ出版.14(8):36-40,2021. |
| ・ |
任智美ほか:総説「教育講演 味覚の基礎と臨床」味覚障害の基礎と臨床.口腔・咽頭科,日本口腔・咽頭科学会,30(1)31-35,2017.
https://www.jstage.jst.go.jp/article/stomatopharyngology/30/1/30_31/_pdf (2024年8月14 日閲覧) |
| ・ | 東加奈子・竹内裕紀:栄養を科学するイラスト解説 味覚障害のメカニズムを探る! 薬剤と味覚障害の関係.Nutrition Care,メディカ出版 14(8):41-45,2021. |
| ・ | 古賀亜希子・菊池由宣:がん患者さんの“食”を守るアセスメントとケア どんなときに起こる?シチュエーション別に学ぶ食の悩みアセスメント&ケア がん薬物療法による悪心・嘔吐、味覚障害(予測的悪心・嘔吐を含む).YORi-SOUがんナーシング,メディカ出版,12(6):17-20,2022. |
| ・ |
厚生労働省:重篤副作用疾患別対応マニュアル 薬物性味覚障害
https://www.pmda.go.jp/files/000245252.pdf (2024年8月14日閲覧) |
| ・ |
小林由佳ほか:特集:がん患者に対する栄養療法と周辺の問題 がん化学療法に伴う摂食障害(悪心嘔吐、味覚異常など)の対策.静脈経腸栄養,日本栄養治療学会,28(2):39-46,2013.
https://www.jstage.jst.go.jp/article/jjspen/28/2/28_627/_pdf (2024年8月14日閲覧) |
| ・ |
藤山理恵・角忠輝:化学療法による味覚障害について.日本口腔診断学会雑誌,35(3)173-182,2022.
https://www.jstage.jst.go.jp/article/jsodom/35/3/35_173/_pdf/-char/ja (2024年8月14日閲覧) |
| ・ | 麻生咲子:がん薬物療法中患者の副作用・症状 これだけ3分解説 シートと動画でやさしく伝える患者アセスメント&ケア 12味覚障害.Yori-SOUがんナーシング,メディカ出版,14(2):52-55,2024. |
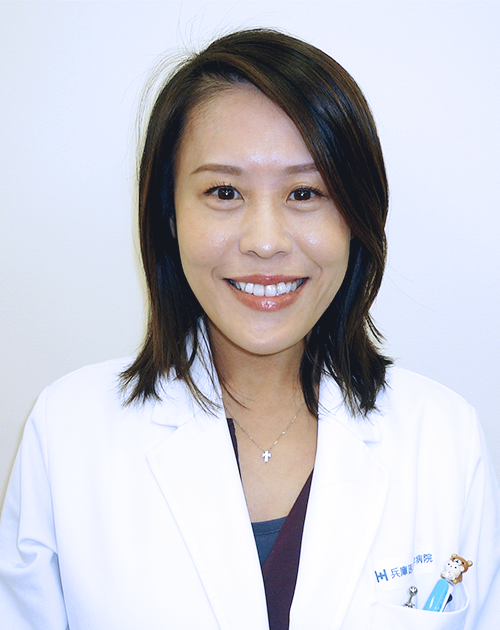
兵庫医科大学医学部耳鼻咽喉科・頭頸部外科
任 智美 先生
2002年兵庫医科大学卒業後、同大学耳鼻咽喉科、神戸百年記念病院耳鼻咽喉科勤務を経て、2009年ドイツ・ドレスデン嗅覚・味覚センターに留学。2011年兵庫医科大学学内講師、2014年同講師に就任。現在に至る。日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会耳鼻咽喉科専門医、日本耳鼻咽喉科学会認定補聴器専門医。日本口腔・咽頭科学会理事、日本味と匂い学会、小児耳鼻咽喉科学会評議員、日本耳科学会会員、日本嚥下医学会会員、日本音声言語学会会員など。専門分野は味覚、幼児難聴、補聴器、漢方治療。
この記事は2024年8月現在の情報となります。

